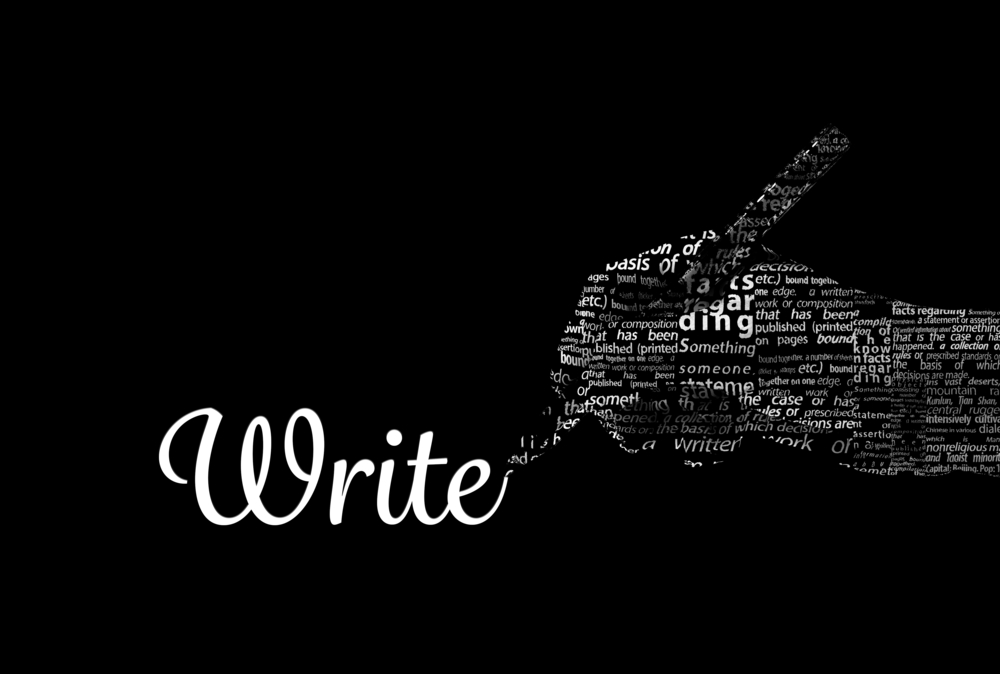<りらいとらぼ>を運営する“しょうろんますたあ”(@ronbun_master
)です。
公務員試験に向けて論文対策を始めてみたけれど、
「 課題文の要約ができない」
「論理的文章が書けない」
「字数不足で原稿用紙が埋まらない」
こんなお困りを感じているあなたのために・・・
今回は<災害対策・減災防災>をテーマとした論文試験について以下の4つを解説します。
1 「災害対策」は超頻出問題です
2 <書写>で論文スキルを磨け!
3 構成メモが答案作成必須ツール
4 重要キーワードを得点源にする
記事の最後に【特別企画】があります!
それでは<頻出問題>の解説からどうぞ!
【本記事はプロモーションを含みます】
「災害対策」は超頻出問題です
次の<問題>をじっくり読み込んで、論文の<答案>をイメージしてみましょう。
問題 「豪雨、暴風、洪水、地震、津波などの自然災害は、時として、私たちの想像を超える力で襲来し、甚大な被害をもたらします。こうした自然災害から県民の生命や財産を守るため、高知県として防災対策を進めるうえであなたが重視すべきと考えるポイントについて、あなたなりの着眼点や現状分析を踏まえて述べなさい」(令元 高知県)
<書写>で論文スキルを磨く
はじめに400字詰め原稿用紙3枚と鉛筆などの筆記道具を用意してください。
次に、ネット等で索出した<模範答案>を最初から最後まで正確に書き写していきましょう。
書写のメリットは3つあります。
メリット
① 合格答案の構成・内容をつかめる
② 原稿用紙の正しい使い方を覚える
③ 答案完成までの時間を確認できる
この<書写トレ>を重ねることで、モチベとスキルは格段にアップします!
原稿用紙のルールについては、以下に整理しておきますね。
原稿用紙ルール ✔︎ 文字は「楷書体」でマスにきちんと収める ✔︎ 書き出し、改行後、段落の先頭は「1マス」あける ✔︎ 行中の句読点(、。)は1マスに入れる ✔︎ 行末の句読点は、文字と共に入れる(行頭に打たない)→行頭禁則 ✔︎ 行中のカッコ(かぎ・まる)は1マスに入れる ✔︎ 行末のカッコ(かぎ・まる)閉じは文字と共に入れる(行頭に書かない) →行頭禁則 ✔︎ 行末のカッコ(かぎ・まる)始めは次行頭に入れる(行末に書かない) →行末禁則 ✔︎ 原則として縦・横書きすべて「漢数字」を用いる ✔︎ 固有名詞、数値、暦年は「算用数字」を用いる ✔︎ 数字は1マスに2字ずつ入れる ✔︎ アルファベットは縦書きに用いないが、固有名詞・略語は大文字で1マスに1字入れる
(横書きには用いることができ、大文字は1マスに1字、小文字は1マスに2字入れる)
構成メモは答案作成必須ツール
 実際の試験場でゼロから答案を作成する場合は構成メモをフル活用すること。
実際の試験場でゼロから答案を作成する場合は構成メモをフル活用すること。
たとえ書きたいことが頭に浮かんできたとしても、
いきなり原稿用紙に書き始めてはダメ!
論文対策ではこれ<鉄則>です。
論文は<序論・本論・結論>の3部構成を基本とします。
したがって構成メモを3つの「箱」で考えます。
序論の箱<現状・問題点>
↓
本論の箱<解決策・取組み>
↓
結論の箱<方向性・まとめ>
この流れで構成メモを作っていきましょう。
構成メモ 序論<現状・問題点>
・日本は世界有数の地震大国
・南海トラフ地震が高確率で発生
・大規模災害への対応は喫緊の課題
・被害を最小限にする対策を推進
↓
本論<解決策・具体的取組み>
・個人や家族での「自助力」強化
・地域での「共助力」強化
・複合災害に対する「公助力」強化
↓
結論<方向性・まとめ>
・行政職員として危機意識を持って職務を遂行
・住民を粘り強く啓発し継続した災害対策を推進
これで頭に中が整理されて、論述の方向性がクリアーになったのでは?
構成メモを書いておけば、答案執筆中にフリーズしてしまうことはなくなります。
ここで「結論」に注目してください。
「ハード面×ソフト面」
「メリット×デメリット」
「二項対置の論法」でバランス感覚を強調しています。
公務員は「公平・公正」の精神を職務遂行のベースにしなければなりません。
日常の業務にも<バランス感覚>が強く求めらる職業です。
論文の中でも「この精神・意識・感覚をしっかり持っています!」とアピールしておくことがとっても重要なのです。
重要キーワードを得点源にする
受験する自治体が独自に展開する「災害対策」に関する情報は、必ずインプットしておきます。
「公式ウェブサイト」をこまめにチェックすること!
「災害対策基本法」「災害時要配慮者」「減災」「ハザードマップ」「自主防災組織」「南海トラフ地震」「首都直下地震」など重要キーワードは、情報収集し、専用ノートに整理しておくことをオススメします。
論述試験で高得点を取るには、あなたが住む自治体の最新情報のインプットは欠かさないこと。そして、日々アップデートしておきましょう。
コレ超重要ですよ。
専門知識と最新情報を駆使できれば、論文の説得力”爆上げ”まちがいないです。
「災害対策」のジャンルに関する知識は、今から積極的にインプットしましょうね。
情報収集に役立つウェブサイトを3つリストアップしておきます。
ぜひチェックしてみてください。
・気象庁公式ウェブサイト
https://www.jma.go.jp/jma/
・内閣府防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/
・総務省消防庁公式ウェブサイト
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/
社会問題の最新情報を網羅する万能テキストを紹介します↓↓↓
公務員試験・論文対策に最適の一冊。
これでガッツリ対策しておけば、あなたの論作文の精度は超速アップしますよ!
【特別企画】です!
公務員試験で合格を狙うなら
まずはこれを見てください!
「小論文の書き方が分からない」
「合格のためのポイントを知りたい」
と思っているあなたに、公務員論文試験<合格への道筋>をお届けします。
・実際の出題テーマに基づいた「答案作成アドバイス」
・小論文が苦手でも簡単に書ける「テンプレート」
・頻出テーマもこれで攻略できる!「模範答案集」
興味がある方はぜひこちらをご覧ください↓↓
https://note.com/337719891126yi/n/n1c5f638c4424
最後に。
・読み手(採点者)の気持ちを慮(おもんばか)って書く
・与えられた問題(課題)に対する結論(答え)を示す
論文対策で肝に銘じてほしいことです。
スキマ時間を大切にして、テキストを読んで、資料で調べて・・・
あとはひたすら書きましょう。
自分が納得いくまで書き続けてください。
日々積み上げた鍛錬のその先に、必ず“合格”への道は開けます。
合格を勝ち取る日まで、ともに励んでいきましょうね。
今回の解説はここまで。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
すべての論文テーマをマスターしてライバルに差をつけるならこちらをクリック↓↓↓
「書くことは考えること。
文章力はきっとあなたの財産となる」
(by しょうろんますたあ_りらいとらぼ)