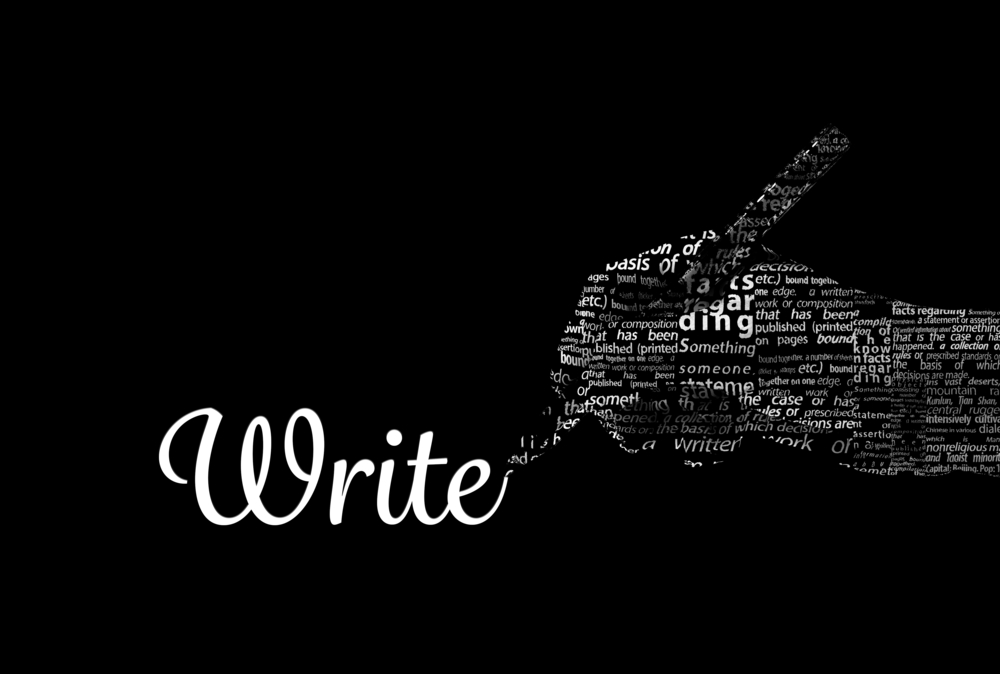こんにちは。
<りらいとらぼ>を運営する”しょうろんますたあ”(@ronbun_master)です。
「原稿用紙を前にしてまるっきり手が動かない・・・」
「筋道の通った文章をサクッと書けない・・・」
小論文対策に取り組んでいるあなた、こんな悩みを抱えているのでは?
この記事で紹介する文章構成法を実践すれば800字程度の小論文は難しくはありませんよ。
私が担当している生徒さんも練習を積み上げて、合格レベルの答案を書けるようになりました。
もしあなたが採点者を納得させる文章を書きたいなら、ぜひこの記事を読み込んでください。
<文章構成スキル>を手に入れれば、必ず合格答案を完成できるはずです。
さっそく文章構成のコツについて解説していきますね。
それでは、どうぞ!
【本記事はプロモーションを含みます】
ひらめいたら構成メモを書く!
思いついたことを直接<原稿用紙>に書き込むのはゼッタイにダメ!
2、3行書いたところで必ず行き詰まります。手が止まり思考もストップします。
原稿用紙がまるで冷凍庫状態に・・・。
文字がすぐに固まってしまい、修正システムが完全にフリーズ!
では、どうすればよいのでしょうか?
家を建てる時には必ず「設計図」をつくりますよね。
だから・・・
原稿用紙はひとまず横において構成メモを書くのです。
小論文は3部構成が基本です。構成メモも3つの<箱>で考えていきましょう。
3つの箱
<序論の箱>
→問題(事実)を入れる
<本論の箱>
→根拠(事例)を入れる
<結論の箱>
→結論(主張)を入れる
モヤッとしていることは3つの箱にすべて書き出してみましょう。キーワードのレベルでよいです。
頭に思い浮かんだことを取捨選択せず、すべて箱に書き出します。
そのあと言葉を整理していくと、少しずつ流れがみえてきます。
これで頭の中がスッキリ、自分の考えもちょっとクリアーになったのでは?
構成メモを書いておけば、執筆中にフリーズしてしまうことはなくなります。
重要なことなのでもう一度くり返します。
× 思いついたことをすぐに原稿用紙に書き込んではダメ!
◯ アイデアはひとまず<3つの箱>に入れておきましょう。
構成メモを作成する3ステップ
構成メモを作成する時のポイントは以下の2つです。
✔︎ まず、3つの箱(序論・本論・結論)をつくる
✔︎ つぎに、キーワード(短い文)をドンドン書き込む
以上!シンプルでしょう?
それでは<3ステップ>で構成メモをつくっていきましょう!
段落構成と字数配分を決める
まず確かめておくことが2つあります。段落構成と字数配分です。
<序論・本論・結論>の3部構成が基本なので、段落(箱)も3つですよね。
800字以上のボリュームであれば、本論を分けて段落を4つにしてもよいです。
ただ、例外もあります。400字程度であれば段落を分けずに書き上げましょう。
字数配分にはいろいろ考え方がありますが
<序論:本論:結論=3:5:2>
およそこれくらいのバランスが目安です。
800字であれば、
<序:本:結=240:400:160>
となります。
まず設問分析と課題文要約から
小論文試験で高得点ゲットのポイントとなるのが<設問分析><課題文要約>の2つです。
まずは<設問分析>からスタートです。以下3つを明らかにします。
✔︎ 問題にしていること
✔︎ 根拠になること
✔︎ 求められる結論
以上3つを明確にして、次のテンプレで自分の意見(主張)を組み立てます。
「私は<問題>について<根拠>から<結論>であると考える」
これが小論文において意見論述を展開するベースとなります。
次は<課題文>への対策です。
<設問1>では課題文を要約させるパターンが主流です。
課題文が提示されていたら通読しながら同時に要約もしておきます。
課題文を読解しつつ筆者の主張(結論)をまとめておくのです。。
筆者の主張に
「賛成か反対か」
「問題はなにか」
「根拠はあるか」
「事例はあるか」
以上4つをチェックしておくと構成メモ作成の準備が整います。
3つの箱で文章構成
<序論・本論・結論>各段落の「箱」を設定します。
そこにキーワード(短文)を書き込んでいきます。
序論の「箱」→考え①(意見)
(課題文の)筆者の主張に対する「意見」です
本論の「箱」→理由+事例
考え(意見)の「根拠」になります
結論の「箱」→考え②(答え)
課題文で提示された問題の「答え」になります
思いついたアイデアをどんどん加えてボリュームアップするとよいです。
書き終えたら以下の2つをチェックしてくださいね。
✔︎ 序論と結論の「考え①②」にズレはないか
✔︎「理由+事例」が(意見・答え)の「根拠」となっているか
スタートしてゴールするまでに<切れ目>や<段差>があれば、語句などを加除修正します。
論理構成がスムーズならここで準備完了。さあ原稿用紙に向かいましょう!
納得させるには結論から書く

採点者が「なるほど!」とひざを打って納得する文章・・・そんな文章をサクッと書きたいですよね。
構成メモを原稿用紙に文章として落とし込む時に使いってほしい型(テンプレ)があります。
以下が、採点者の納得感をアップさせる文章化テンプレートです。
究極のテンプレ
【考え①(意見)】
→「私は〜と考える(提案する)」
【根拠①(理由)】
→「なぜなら・・・からだ」
【根拠②(事実)】
→「事実・・・となる」
【根拠③(事例)】
→「実際・・・であった」
【考え②(結論)】
→「だから・・・と考えるのである」
この【5層構造】を意識するだけで、文章が論理的になります。
分かりやすい文章、採点者にサッと伝わる文章になります。
論理的文章をどんどん積み上げて高得点を必ずゲットしましょうね。
解説まとめ&特別企画
まず今回の解説内容のポイントは以下の3つです。
✔︎ いきなり原稿用紙に書き込まない。
✔︎ 構成メモを作れば文章は論理的に展開する。
✔︎ 問題→考え①(主張)→根拠(理由+事実+事例)→考え②(答え)で論理的文章になる。
そして今回の特別企画は・・・
小論文試験で合格を狙うなら
まずはこれを見てください!
「小論文の書き方が分からない」
「合格論文作成のポイントを知りたい」
と思っているあなたに、大学入試で出題される論文テーマに対する<合格への道筋>をお届けします。
・実際の出題テーマに基づいた
「答案作成アドバイス」
・小論文が苦手でも簡単に書ける
「究極のテンプレート」
是非この機会に<合格への道筋2点セット>をご入手ください。
↓詳細はこちら↓
https://note.com/preview/naa874ba79ba6?prev_access_key=a290256c293e6f80cbdc7915bf9fb834
今回の解説はここまで。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
これからあなたの<文章力>しっかり磨いていきましょうね!
小論文の基本対策を万全にして、ライバルに差をつける記事はコチラです↓↓
![]()
「書くことは考えること。
文章力はあなたの財産となる」
(by しょうろんますたあ_りらいとらぼ)