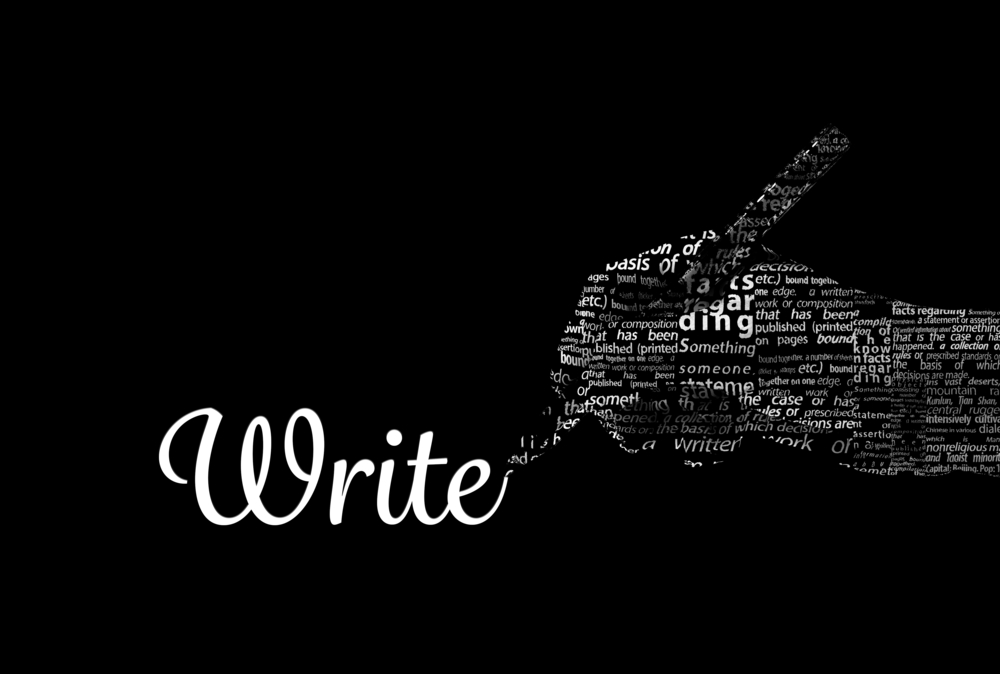小論文試験で合格を狙うなら
まずはこれを見てください!
「小論文の書き方が分からない」
「合格答案作成のポイントを知りたい」
と思っているあなたに、大学入試で出題される論文テーマに対する<合格への道筋>をお届けします。
・実際の出題テーマに基づいた
「答案作成アドバイス」
・小論文が苦手でも簡単に書ける
「究極のテンプレート」
是非この機会に<合格への道筋2点セット>をご入手ください。
↓詳細はこちら↓
https://note.com/preview/naa874ba79ba6?prev_access_key=a290256c293e6f80cbdc7915bf9fb834
あらためまして!
<りらいとらぼ>を運営する“しょうろんますたあ”(@ronbun_master)です。
大学入試にチャレンジするあなたのために小論文対策の重要ポイントを7つの記事にまとめました。
小論文対策を始めるタイミングで一気読みするのが超オススメです!
<対策記事>のラインアップは以下の通りです。 600字答案作成法 記事① 合格答案の書き方
<基礎対策>編
記事② 合格答案の書き方
<単語・文>編
記事③ 合格答案の書き方
<文章構成>編
記事④ 合格答案の書き方
<論理構成>編
記事⑤ 合格答案の書き方
<構成展開>編
記事⑥ 合格答案の書き方
<課題文読解>編
記事⑦ 合格答案の書き方
<統計データ>編
合格答案作成の重要ポイントをコスパよく学んで、志望大学合格をゲットしましょう!
【本記事はプロモーションを含みます】
合格答案の書き方<基礎対策>編

まず小論文を書く目的をハッキリさせましょう。
✔︎ 採点者を論理的文章で納得させる
✔︎ 答案が評価されて高得点をゲットする
✔︎ 志望する大学に見事合格する
ズバリ!以上の3つです。
では採点者を納得させる答案の条件とは?
読みやすい文章でスッキリ内容を伝えられること。
大切なのは読み手の気持ちを慮(おもんばか)る<想像力>です。
これを踏まえたうえで、小論文対策をどう進めればよいか?
やることは2つだけ。
<ミッション①>
文章を書いて、スキルを高める
<ミッション②>
情報を集めて、知識を増やす
どうです? とてもシンプルでしょう?
<情報・知識>には3つのジャンルがあります。
・自己体験
・社会問題
・専門的内容
社会問題と専門的内容に関してはコツコツ積み上げていきましょう。
いわゆる<ネタ集め>ですね。
トレンドワードを勉強するのにとても重宝する2冊を紹介します!
あとは小論文のスキルアップをめざすための<毎日やることリスト5>です。
原稿用紙に向かうと同時にぜひ実践を!
リスト5
① 読書をする
② 新聞を読む
③ 日記をつける
④ 情報をファイルする
⑤ 授業を真剣に受ける
合格答案の書き方<単語・文>編
「単語」の並びを整えるだけで文章は格段に読みやすくなります。
要チェックの単語の関係(並び)は以下3つです。
1 <主語・述語>の関係
2 <修飾語・被修飾語>の関係
3 <主述・修飾並列>の関係
なかでも<主語・述語関係>は基本なのでキッチリ押さえてください。
ダラダラと長文を書いてしまう人はとくに気をつけましょうね。
文章の意味関係がねじれてしまってとてもキケン。採点者を不愉快にさせてしまう結果に・・・
✔︎ 意識して短い文を書くこと
✔︎ 主語→述語のペアリングを意識すること
✔︎ できるかぎり主語+述語を近づけること
採点者に気持ちよく答案を読んでもらうため、以上3つのポイントはいつも心がけておきましょう。
「単語」から「文」構成のテクニックはこちらの記事をご覧ください↓↓
合格答案の書き方<文章構成>編
文と文が正しい関係を持つことで論理的な文章が構成できます。
ここでは接続語が大活躍します。
接続語
① 順接・説明
「まず」→論述のスタートを示す接続語
他にもこんな接続詞が登場します。
「そこで」(視点の提示)「ならば」(総括の場面)「なぜなら」(根拠の提示)
「よって」(結論の場面)
② 並列・添加
「また」「そのため」→文と文をつなぐ、根拠にする接続語
他には「さらに・そして」(論述の方向づけ)もあります。
③ 換言・例示
「つまり」→別の表現で言い換える接続語
他には「要するに・すなわち」(換言)もあります。
「たとえば」→具体例で言い直す接続語
④ 逆接・対比
「だが」→内容に反対する接続語
他には「しかし・けれども」(逆接)もあります。
「これに対して」→相反させ比べる接続詞語
他には「一方で」「他方で」(対比)もあります。
「~ので、・・・」「~が、・・・」「~し、・・・」「~ため、・・・」「~だから・・・」など
接続語によく似たワード、これらぜーんぶまとめて接続助詞
接続助詞は便利ですが多用は禁物です。連続して使うのは2つまで。
接続語を正しく使って文を区切るとわかりやすい文章になります。
短文を重ねると文章にリズムも出てきますよね。
文を理論的な「文章」にする方法はこちらの記事をご覧ください↓↓
合格答案の書き方<論理構成>編
小論文を書く時、ついやってしまう<3大ミス(禁じ手)>
✖️ 別の論点を加えてしまう
✖️不要な文を加えてしまう
✖️ 自己体験のみを根拠にする
以上3つは「字数かせぎ」になり「ストレス文章」を量産してしまいます。
ここは読み手(採点者)の存在をしっかり意識しましょうね。
小論文を読んで合否を決めるのは採点者ですから。
ミスを防いでくれる最強ツール<紙上対話>について解説します。
採点者はいちいちツッコミを入れながら、あなたの小論文を読んでくれます。
ツッコミとは<疑問><反論>のこと。
そこを逆手にとって答案を構成すればよいのです。
以下( )がツッコミです。 紙上対話 ワクチン接種に一定の効果は認められるが、すべての国民に義務化することには反対だ。 一人一人の体質や健康状態は様々であり、すべての国民が一斉には接種できないからだ。 たとえば、副反応による体調不良によって仕事や学業に支障をきたすデメリットが考えられる。 確かに、家族全員がワクチン接種を受ければ安心して生活できるし、同居する高齢者の重症化リスクも軽減する。
(反対派なのですね。なぜそう考えるの?)
(なるほど。確かに個人差に配慮するのは大切だけど、それだけで反対する理由にはならないよね。感染拡大すれば犠牲者がたくさん出るかも)
(えっ?デメリットだけ?それって接種を受けたすべての人に当てはまること?)
(おっと、メリットを述べて賛成派の主張を認めたね。で、結論は?)
このように、自問自答しながら書き続けます。一人二役で対話している感じです。
この方法は相手の質問に正面から答えることが超重要です。
ここさえ守って練習を積めば、筋道の通った小論文ができあがります。
小論文をレベルアップする詳細はこちらの記事をご覧ください↓↓
合格答案の書き方<展開構成>編
 構成メモは以下のフローで作成しましょう。
構成メモは以下のフローで作成しましょう。
<問題(テーマ)>
↓
<結論(主張)>
↓
<根拠(理由)>
根拠を<説明><補足><換言>で構成すると文章にボリュームがでて読み手にしっかり伝わるようになります。
さらに<反論想定>のテクニックも使います。まず反対意見を認めた上でそれに再反論するスタイルをとります。
これは「確かに・・・しかし・・・」構文とも呼ばれます。
自分と異なる意見、対立する意見を一旦認めて、反論するので説得力アップすること間違いナシ。
そして結論は<意見>+<解決策>でカッコよくフィニッシュしましょう!
構成メモは<テーマ型>小論文にも威力を発揮しますよ。
テーマ型は賛否択一型で論述できないので、問題を設定する必要があります。
問題設定は以下の3つが定番でしたよね。
「なぜ・・・か」
(原因パターン)
「どんな問題が・・・」
(影響パターン)
「どんな方法で・・・」
(解決パターン)
以下のフローで構成メモを作っておけば、下書きは超スムーズにできますよ。
(問題)
↓
<原因分析>
↓
<影響分析>
↓
<問題解決>
↓
(結論)
テーマ型小論文の答案作成は、構成メモを書いておくと気持ちに余裕が生まれます。
小論文をボリュームアップして高得点をねらう詳細はこちらをチェックしてください↓↓
合格答案の書き方<課題文読解>編
<課題文>型小論文の「設問」は、ほとんどが以下のようなパターンです。 課題型小論文 <設問1>要約
↓
<設問2>用語説明
↓
<設問3>論述
<要約問題>には必ず構成メモを作成しましょう。
構成メモは<問題>→<根拠>→<結論>のフローでしたよね。
まず、筆者の主張を特定して<結論>とします。
次に、結論に対応した<問題>を考えます。<尾>から<頭>へ逆行するイメージです。
<問題>は省略されることが多いので、推定自作してもよいです。
最後に、課題文から<根拠>となる文章をピックアップします。
<問題><根拠><結論>の3つそろえて文章化すれば<要約問題>の答案は完成です!
<論述問題>は、
「~についてあなたの考えを◯◯◯字以内で述べなさい」が一般的です。
答案は以下の2パターンが考えられます。
① <賛成・反対>の択一型
② <原因・影響・解決>の分析型
②<分析型>の答案作成については、テーマ型小論文のチャプターで解説しました。
ここでは①<択一型>で演習しましょう。
設問 「監視社会」のあり方についてあなたの考えを600字程度で述べなさい。
まずは設問分析でしたよね。
分析のポイントは「~について考えを述べる」の部分です。
この設問、<分析型>のように見えますが、ここは筆者の主張を軸にします。
たとえば筆者の主張を<監視社会の見直し>とします。
この主張に対してあなたは<賛成><反対>どちらの立場で論述しますか?
専門家の意見に反論するのはハードル高いですよね。ここでは<賛成>で論述をすすめましょう。
答案は「択一型」で構成します。設問分析のつぎは構成メモの出番です。
構成メモ <問題>
監視社会を<強化する><見直す>どちらがよいか。
↓
<根拠①>
監視する側も人間で、ミスやエラーを犯す存在である。
<根拠②>
個人情報が流出すればプライバシー侵害は避けられない。
↓
<結論>
監視社会は見直すべきだ。
<根拠>をさらにもうひとつ加えます。
<根拠③>
啓発活動などで道徳心を醸成すれば過度な監視は不要となる
根拠①②で「監視あり」のデメリットを指摘しておく。
根拠③で視点を変えて「監視なし」のメリットをあげるところがミソ。
実際の答案では「これらに加えてもうひとつ理由がある」という前置きをして論述するとよいです。
どうしても根拠を思いつかない時は、防犯カメラにまつわる体験や情報をしぼり出してみましょう。
課題文型小論文の要約と論述問題は、構成メモを書くと答案作成がスムーズです。
これで高得点ゲットまちがいなし!
合格答案の書き方<統計データ>編
「統計データ型」小論文の試験で登場するグラフは4タイプです。
<折れ線グラフ><棒グラフ>
<帯グラフ><円グラフ>
資料をただ眺めていても時間が過ぎていくだけ。まず2つの「声」に耳を傾むけてみましょう。
1つ目はグラフからの声です。
グラフのトレンド(傾向・変化)をつかむこと。ポイントは「最高値(山)」「最小値(谷)」「差異」の3つだけ。
2つ目は出題者からの声です。
提示されたグラフから<問題>をあぶり出すこと。
ポイントは
「なぜ(原因)」「どんな(影響)」「どうすれば(解決)」の3つです。
次に<折れ線グラフ><棒グラフ>それぞれの資料で演習してみましょう。
折れ線グラフ
折れ線グラフを見て・・・
「〇〇が年間通じて増え(減り)続けている。特にこの期間の差は大きいぞ」
以上が<グラフからの声>です。つぎは<出題者からの声>です。
「なぜ〇〇は増え(減り)つづけるのか」<原因>
「増え(減り)つづけた場合どんな問題が生じるのか」
<影響>
「どうすればこの流れを変えられるのか」<解決>
<原因><影響><解決>で問題設定し、結論(答え)を出す流れで答案を作っていきましょう。
答案の最後は<解決策>でしめくくるのがベストです。
棒グラフ
棒グラフを見て・・・
「〇〇における国際比較、先進国10ヶ国のなかで日本は最下位だ!」
これが<グラフからの声>です。つぎに<出題者からの声>です。
「なぜ日本の〇〇は先進国のなかで最下位なのか」(原因)
「どうすればこの状況を改善できるのか」(解決)
<2つの声>で問題を設定できたら、次は設問の分析にかかりましょう。
ケース①(折れ線グラフ)で解説します。
設問
季節性インフルエンザの感染拡大を抑制するためどのような対策を講じていけばよいか。600字程度で論じなさい。
「どのような対策を講じればよいか」に対して結論(答え)を出す<解決型>です。
3つの<問題>に対して<結論>を出すフローで構成メモを書いていきます。
構成メモ
<問題①>
なぜ感染者が増えつづけるのか
(原因)
↓
<結論①>
ウィルスが変異して感染力が高まったから
<問題②>
感染者が増えつづけるとどんな問題が生じるのか(影響)
↓
<結論②>
診療機関に発熱患者が殺到して、医療ひっ迫や崩壊を起こす
<問題③>
どうすれば感染拡大を抑えられるか
(方法)
↓
<結論③>
感染防止対策を徹底させ、軽症者は自宅で療養させる
これで構成メモは完成です。これをベースにして、
<変異ウィルス><医療現場><感染対策>などの情報を加えて字数をボリュームアップしていきましょう。
以下のような書き出しで答案を作っていくとよいです。
解答例 資料からは、大型連休後に新規感染者が急激に増加していることがわかる。外国人観光客によるオーバーツーリズムなども背景にあると考えられる。そこで本論文では、感染拡大を抑制するための対策について考察し論じていく。
そもそも新規感染者はなぜ急増しているのか。いくつか原因は考えられるが・・・
「統計データ型」小論文はグラフの<2つの声>を聞くところからスタート!
ここをマスターできれば統計データ型の答案作成はだいじょうぶですよ。
「統計データ型」小論文の詳細はこちらの記事をご覧ください↓↓
<小論文超対策note>が完成しました!
 今回の特別企画は・・・
今回の特別企画は・・・
小論文試験で合格を狙うなら
まずはこれを見てください!
「小論文の書き方が分からない」
「合格論文のポイントを知りたい」
と思っているあなたに、大学入試で出題される論文テーマに対する<合格への道筋>をお届けします。
・実際の出題テーマに基づいた
「答案作成アドバイス」
・小論文が苦手でも簡単に書ける
「究極のテンプレート」
是非この機会に<合格への道筋2点セット>をご入手ください。
↓詳細はこちら↓
https://note.com/preview/naa874ba79ba6?prev_access_key=a290256c293e6f80cbdc7915bf9fb834
そして最後に。
ぜひ肝に銘じてほしい、とても大切なポイントを2つお伝えします。
・読み手(採点者)の気持ちを慮(おもんばか)って書くこと
・与えられた問題に必ず結論(答え)を出すこと
短い時間でかまいません。毎日読んで、調べて・・・
そして納得いくまで書き続けましょう。
同じ問題に何回チャレンジしてよいのです。
日々練習を積み上げたその先に合格への道は必ず開けます。
合格を勝ち取るまで、ともに励んでいきましょうね。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
「書くことは考えること。
文章力はきっとあなたの財産となる」
(by しょうろんますたあ_りらいとらぼ)